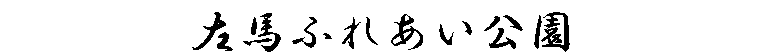 |
||
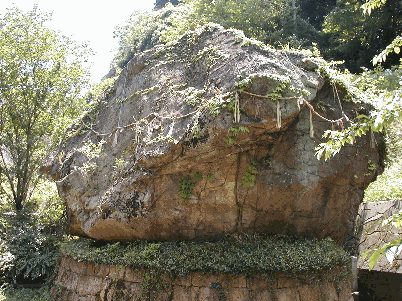 |
5月6日の年号が馬の後ろ足の横にあったが 摩滅してしまったことが記されています |
|

|
数百トンの花崗岩の下部、奧の方に、後ろ足を跳ね上げ 躍動する馬が実に写実的な表現で半肉彫されています。 平安時代後期に水神として造立され、江戸時代には、 女芸(裁縫、茶法、生け花、舞踊など)の上達の神として 信仰を集め、 遠く京都や大阪からも参拝する人も多かったと聞きます。 駒岩は、もともとこの場所にあったわけではありません。 もとは玉川の水源に祀られていた雨吹龍王祠(水分神社) の傍らにありましたが、昭和28年8月の南山城水害時に 祠もろとも流出し玉川の谷底へ落ちてしまったのです。 水害後は見ることは不可能とされていましたが、 地元の方々の努力で土を掘り下げ、 下から見上げる形で見る事が出来るようになりました。 そして駒岩を中心に「左馬ふれあい公園」として 整備されました。 |
|
